88歳の長澤志保子さんは、1945年8月15日を「人生で一番うれしかった」と振り返る。空襲で近所の人が頭を撃たれて亡くなり、通学路には遺体が転がる――。そんな恐怖の日々が終わりを告げたからだ。だが、戦争の苦しみはその後も続いた。
【平塚雄太】
長澤さんは東京で生まれ育った。四谷の国民学校(現在の小学校)に通っていたが、父が出征し、戦況が悪化してきた1944年12月、一家で母の実家があった千葉市蘇我町(現・中央区蘇我町)に疎開した。
ただ、千葉も安全ではなかった。既に日本本土は米軍の爆撃機B29の攻撃圏内。千葉付近の上空をよく通り、頻繁に警報のサイレンが鳴った。
そのたびに一家は山の防空壕(ごう)まで約3キロの道を1時間近くかけて避難した。当時8歳だった長澤さんは母とともに3人の弟や妹を連れて歩く。夜に出て朝まで壕の中という時もあり、6歳の弟は「もう逃げるのやめようよ」と嫌がった。
次第に身の危険が増していく。45年5月のある日、米軍の小型機が自宅近くに襲来し一帯に機銃掃射を始めた。「ダダダダダ」とけたたましい音が鳴り、長澤さんは急いで押し入れの中に逃げて布団をかぶった。
家の窓ガラスは割れ、4発の弾が見つかった。近所では頭や腹を撃たれて亡くなった人もいた。
それ以来、飛行機が近くを通るたびに地面に伏せ、「生きた心地がしなかった」という。千葉は6月10日、7月7日に本格的な2度の空襲を受ける。長澤さんは2度とも防空壕で難を逃れたが、6月の空襲で蘇我町は大きな被害を受け学校の友達も亡くなった。
通学路の道路脇には、モンペをはいた人の足首が落ちていた。「引き取り手がいない遺体だろうか」。学校の行き帰りで何度も目にし、やりきれない思いをした。
こうした日々を過ごしていたため、敗戦を告げるラジオの「玉音放送」を聞いた母が「日本が負けた」と言った時は、喜びを隠せなかった。「もう毎晩のように逃げなくていいんだ」と外に飛び出し、晴れ渡る青空に向かって両手を広げた。
「母には『まだ危ないかもしれない』と、家の中に入るように怒られました」。思い出して長澤さんは苦笑する。
しかし、戦争による苦労は終わらなかった。
戦後しばらくは食糧難に苦しみ、タニシ、野草、カエルなど食べられるものは何でも食べた。一時は栄養失調で倒れて生死の境をさまよった。
直前まで一緒にかくれんぼをしていた同学年(国民学校3年、今の小3)の女の子が、不発弾の爆発で死亡したこともあった。東京大空襲を生き延びて千葉に来た子だった。長澤さんは「せっかく戦争が終わったのにね」と声を落とした。
長澤さんは成人してから放射線技師として働き、退職後は自宅のある四街道市内の小学校で戦争体験を語ってきた。がんを患って一時入院したことをきっかけに、自分が亡くなっても後世に体験を残したいと、2020年に紙芝居を制作。「戦争を無くすためにできることをしたい」と、これからも体力の続く限り伝える活動をしていくつもりだ。
「なぜ人間同士が殺し合わなくてはいけないのか。今も世界各地で戦争が起きており、決して人ごとではない。若い人にも自分のこととして考えてほしい」





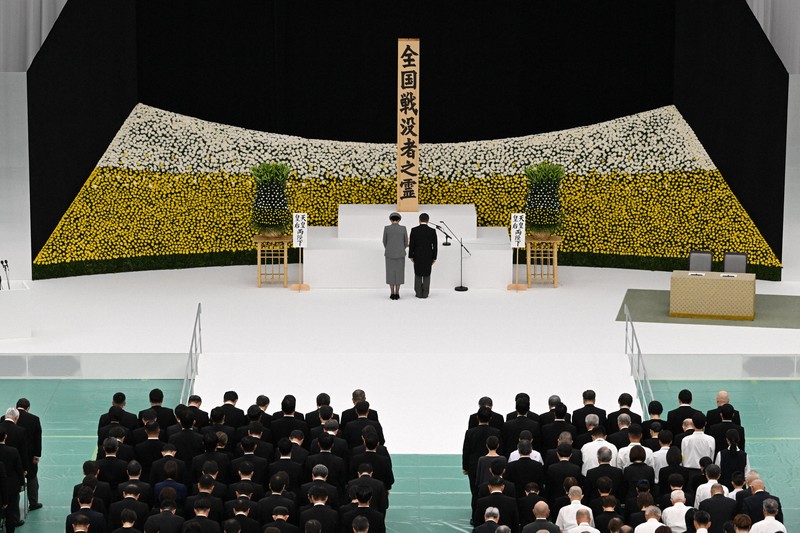
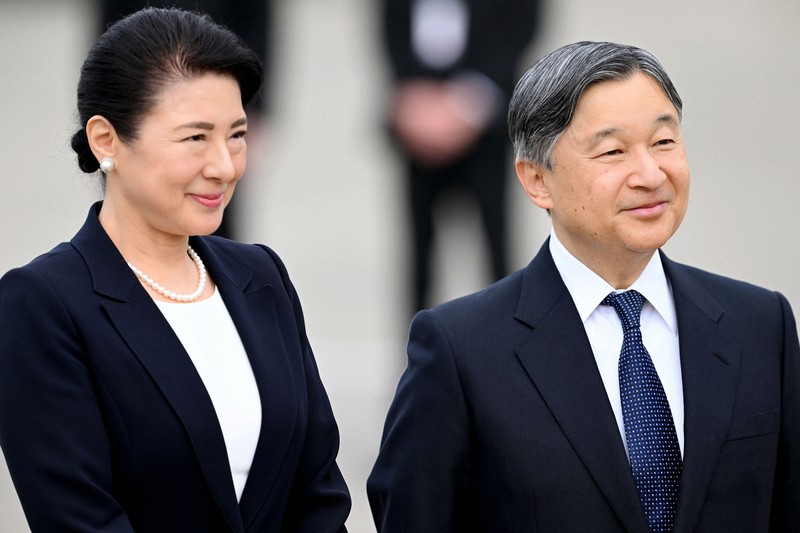


Comments