
「死んでたのにさ、それを連れて帰って来たんだからね。あれだけは強烈」
長崎県佐世保市俵ケ浦町出身の吉村栄子さん(86)=神奈川県在住=は6歳だった1945年夏の記憶を忘れることはない。原爆が落とされた8月9日、長崎市内には学徒動員で兄高原昭三さん(当時16歳)がいた。投下の一報から父定之さん(同39歳)は長崎市へ向かった。
「帰ったぞー」。父に背負われ帰宅した兄はすでに息絶えていた。自宅の縁側で横たわる兄の姿が栄子さんの目に焼き付いている。
連れ帰ったのが何日だったか、その場に家族の他に誰がいたかという記憶はない。昭三さんの墓には、死亡日として届け出の日と思われる8月18日が刻まれている。
長崎原爆戦災誌などによると、原爆投下当日以降、市内から各地へ負傷者を運ぶ「救援列車」が運行された。
「死んだと思われないよう、もう少しだよ、がんばるんだよとか、しゃべってしゃべって」。父から聞いたのは、大村湾沿いを走る列車で帰宅する道中ずっと兄に話しかけていたこと。遺体だと分かると乗車を断られる可能性があったという。「もう死んでたんだけど、じいちゃん(父)が連れて帰ったってだけでうれしくて、うれしくて」と栄子さんは振り返る。
列車で運ばれた負傷者は、沿線の病院や学校などの救護所で手当てを受けた。
各地には当時の様子を伝える碑が建立されている。また、救護活動の記憶を継承する住民の取り組みが現在も続いている。
「列車の中は生き地獄。こんなひどい爆弾が世の中にあるのか」と思った。15歳だった氏原和雄さん(95)は長崎市からほど近い諫早駅で列車から負傷者を降ろす作業を手伝った。
娘の鶴田光恵さん(65)ら「長崎被災協・被爆二世の会・諫早」は父の体験などを紙芝居にし被爆経験を伝える。高齢の氏原さんは「核のない世の中ができるよう、紙芝居を活用してほしい」と思いを強める。
原爆の負傷者はさらに県央の町や県北の佐世保市などにも運ばれた。
10年前に発足した「松原の救護列車を伝える会」は、県央の大村市松原地区の十数人の体験談を基に朗読劇などにまとめている。5月には松原駅から小学校への搬送を手伝った当時10歳の男性らに聞き取りをした。メンバーの村川一恵さん(49)は「80年前の記憶を直接聞く最後の機会だとの思いです」。【和田大典】
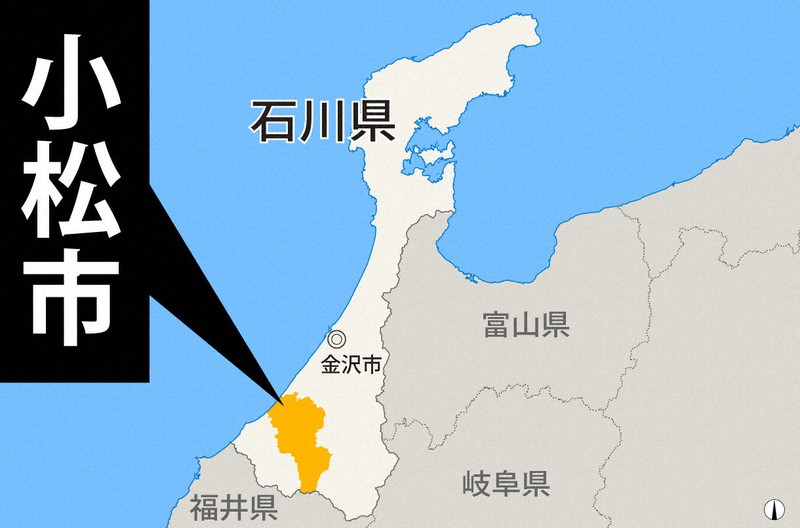







Comments