
「黙っているしかなかった」。淡々と語った言葉に、かつての深い孤独がにじんでいた。
長崎で被爆した大城智子さん(84)=沖縄県浦添市=は、終戦翌年から沖縄で暮らす。1972年まで米国の統治下で、被爆者援護も本土より遅れた地。長い間、自分の境遇を周囲に語らなかった。それを変えたのは、島の被爆者たちとのつながりだった。
那覇市出身の父備瀬知祐(びせちゆう)さん(2004年に93歳で死去)と母幸子さん(06年に95歳で死去)のもと、大阪で生まれた。4歳だった45年春、父方の祖母と同居するため長崎市本原町に引っ越し、1歳の弟を含む5人で暮らした。
8月9日の午前11時2分。爆心地から約1・3キロの自宅で祖母と弟と遊んでいると、大城さんの頭の上に天井が崩れ落ちてきた。
「智ちゃん、智ちゃん」。友人宅から自宅に戻ってきた母の声が聞こえ、がれきの中から必死に「助けて」と叫んだ。母はやけどを負った大城さんを救出すると、胸に抱いて救護所を目指した。母の手記によれば、祖母は爆風に吹き飛ばされ救護のかいなく死亡。祖母に背負われていた弟は土壁に挟まれ即死した。
46年に沖縄へ。両親はげた作りや溶接工をして生計を立てた。被爆者の中には、原爆を投下した米軍の基地関係で働く人も多かった。
生きるための選択は被爆者の口を重くした…

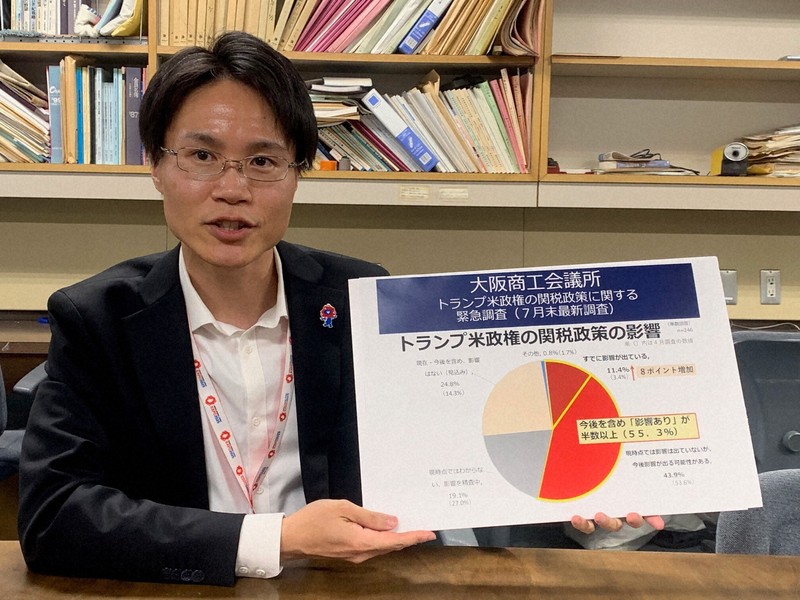



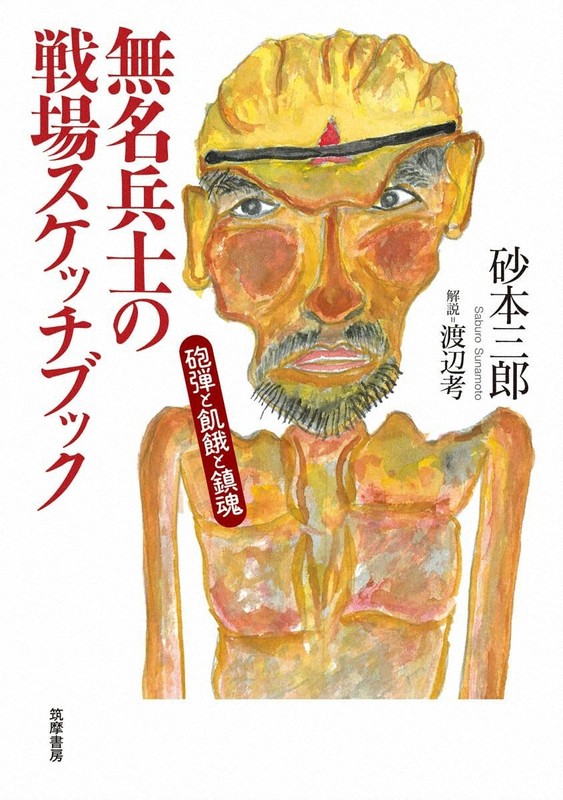

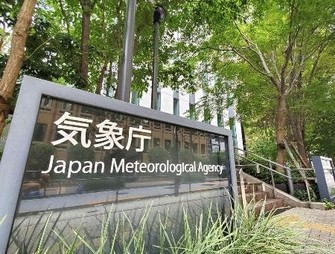
Comments